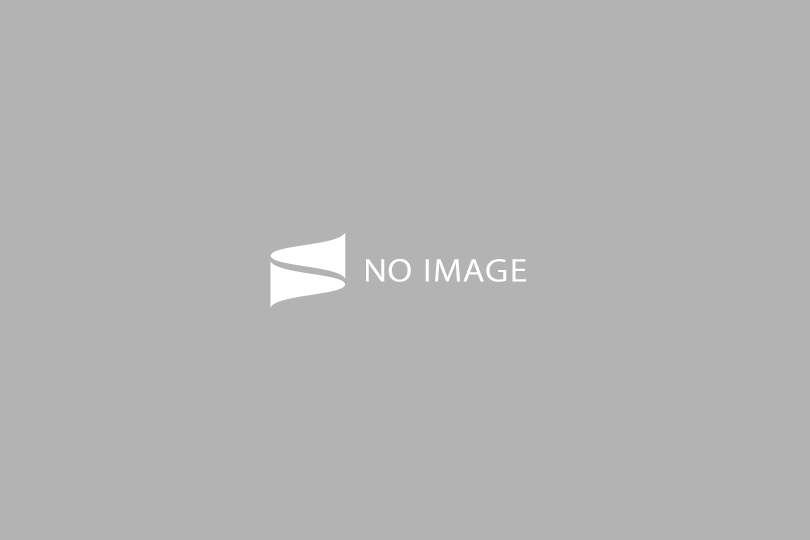夏といえば、花火大会、浴衣、そして屋台!
でも最近、「屋台の牛タンが実は豚タンだった」「衛生的にかなりやばい」なんて話がX(旧Twitter)で話題になってます。
実際にテキ屋でバイトしてた人の暴露投稿もバズってて、「マジか…」と思った人も多いはず。
今回はそんな**“屋台ってほんとに安全?”問題**を、SNSでの反応・体験談を元にゆるっとまとめてみました。
見たいとこをクリック
「屋台牛タン串偽装」が議論のきっかけ
高校生の頃、テキ屋(祭りや夜店の屋台)で夏場だけ毎年アルバイトしてた。
— アスパラ社長 (@ShintaniManabu) August 3, 2025
添付写真の投稿が物議を醸していたが、全く驚かない。
本当はさらに闇が深いのでそれを暴露していこうと思う。
(続く) pic.twitter.com/nwDMdVfBIq
投稿概要(画像やインプレッション)
→ SNSで拡散された投稿は、屋台で販売された“仙台牛タン”の写真付きで、表示回数は900万超え。
牛タン800円 → 実は豚タン
→ 写真の商品が牛タンとされていたが、実際は安価な豚タンだったと指摘され話題に。
「客舐めてんな」との声、多数
→ 見た目や価格のギャップに、ネット上では「詐欺では?」という批判の声も多数。
串にした時のコスト感


たとえば1本の串に50g使うとすると…
| 種類 | 1本あたりの原価(ざっくり) |
|---|---|
| 牛タン | 約125〜200円(※良質なものだと300円以上) |
| 豚タン | 約20〜40円程度 |
💥 原価差のインパクト
- 見た目が似ていることを利用して、豚タンを「牛タン」として販売すれば、原価が5〜10分の1に抑えられます。
- 800円で売れば、原価率は5%未満になることも(完全に“ボッタクリ”構造)。
仮に牛タン串→豚タン串だった場合は、売った分が全て利益になるほど儲かる仕組みなのでしょう。
実際のところの事情は不明ですが、火のないところに煙は立たない・・・事実かもと思ってしまう。
屋台(テキ屋)の衛生管理は実際どうなの?
ここからは屋台の衛生管理って実際にどうなの?という部分に触れていきたいと思います。
常温で何時間も放置?
→ 食材をクーラーボックスに入れず常温で放置している屋台もあり、食中毒リスクが高まる。
手袋なし・素手で串刺し
→ 調理中に手袋を使わず、素手で食材に触れるケースも珍しくなく、不衛生との声も。
使用済みタレの再利用?
→ 一部では、何人もがつけたタレを再利用する例もあり、衛生管理が疑問視されている。
屋台営業は法律のもとで管理されている
屋台といえど“無法地帯”ではなく、祭りやイベントでの営業にも食品衛生法に基づくルールが適用されます。
営業には保健所の許可が必要で、水の確保・設備・ゴミ処理などの衛生基準をクリアしなければ出店不可。
食中毒が起きるリスクは?
統計のデータでは、屋台起因の食中毒は全体のごく一部のようです。
ただし、炎天下や簡易設備での調理という特殊環境ゆえ、保存状態や調理器具の使い回しには注意が必要です。
実際に、調味料や生ものが原因で軽度の食中毒が起きた例もあります。
安心できる屋台の見分け方(自衛術)

保健所の表示がある屋台を選ぶ
→ 「営業許可証」が掲示されている屋台は、運用ルールなどをしっかり遵守している可能性も高い。
明らかに“安すぎる”肉は注意
→ 牛タンなどの高級食材がワンコインで出ていたら、代替肉や加工品の可能性を疑うべき。
混雑してる屋台は回転が早くて安全
→ 人が多い屋台は食材の回転が早く、長時間放置されにくいため食材が傷みにくく比較的衛生的。
屋台の安全性を見極めるチェックポイント
以下の点を観察すると、ある程度の衛生管理レベルが判断可能です。
- 店員が手袋や帽子をしているか
- 調理と会計の場所が分かれているか
- 食材の保存にクーラーボックスや冷蔵庫が使われているか
- 手洗いや消毒の設備が用意されているか
忙しいながらもリスク管理を行っているかどうかが注目ポイントですね!
SNSの反応とバズの広がり方
「またかよ」「昔からあるよね」的反応
→ 一部のユーザーは屋台のこうした問題に慣れており、驚かないという反応も見られた。
炎上より“納得感”で拡散したケース
→ 批判というより「やっぱりな」と納得する声が多く、共感型で広がったのが特徴的。
この時期になると毎回話題に上がってくる夏祭り屋台問題、しっかり営業してる屋台とそうでない屋台、安全に楽しむ為にも最低限の知識は持っておきたいですね。